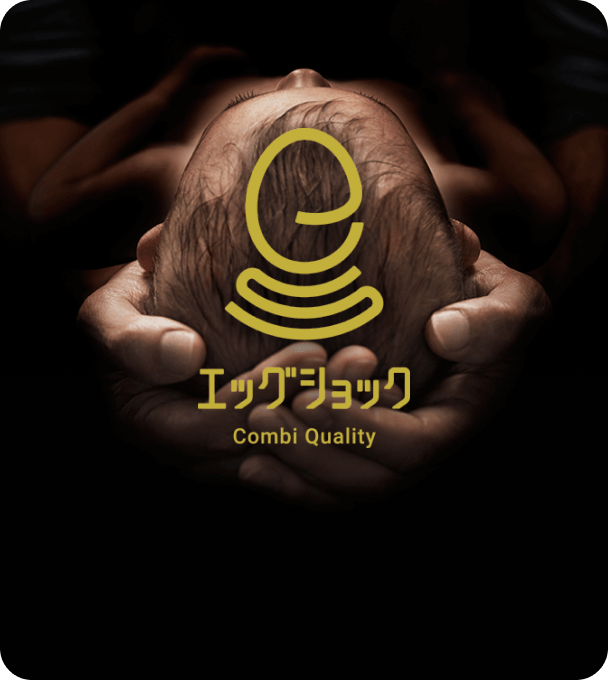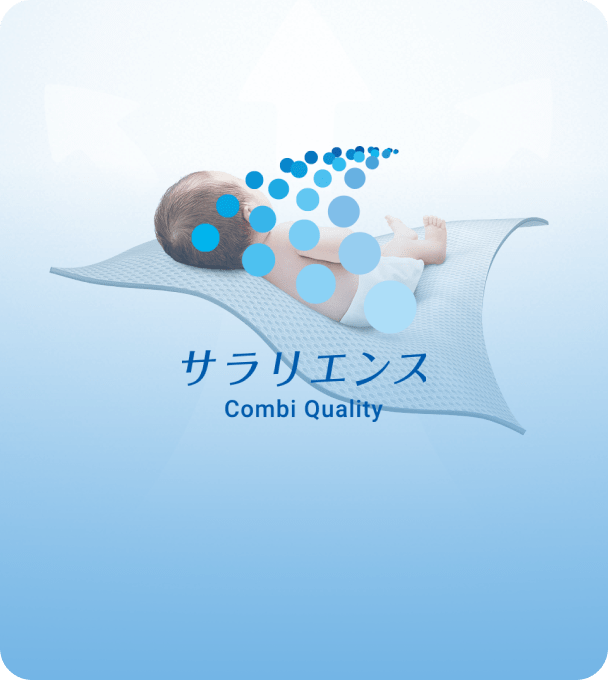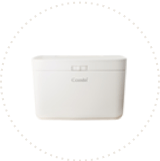Baby Life
Design.
赤ちゃんを育てることが、
楽しく幸せだと思える社会をつくる。
About Combi
豊かで夢のある生活文化を
創造することを目指して
ベビー用品の総合メーカーとして、
「育児をする人と赤ちゃんのコンビを応援する」企業を目指して、
今までにない製品・サービスを世に出し、
育児環境の向上に努めてまいります。



Recommend おすすめコンテンツ
はじめてのベビーグッズ選びをもっと楽しく!
コンビ
プレママ・プレパパレッスン
赤ちゃんとの生活をイメージしながら、ベビーグッズ選びのポイントをお伝えする、第一子マタニティ向けイベントです。
来場形式の体験型レッスンと、自宅からリラックスして参加できるオンラインレッスンがあります。参加者にはもれなくプレゼントも!